資産運用には、株式投資や投資信託など、さまざまな方法があります。その中でも比較的リスクが低い方法として注目を集めているのが「債券投資」です。この記事では、債券投資の基礎知識やそのメリット、リスクなどについて解説します。債券投資について興味がある人は、ぜひ参考にしてください。
債券投資とは
「債券」とは、国や企業などが投資家からお金を借りる際に発行する有価証券のことを指します。債券投資とは、投資家が政府や地方公共団体、企業などに対して「債券」で投資することです。
国や企業などの発行体は投資家に借金することになるため、投資家に対して支払い義務と利子が発生します。そのため、基本的に債券投資では、発行体の財務状況が悪化したり、信用状況が失墜したりしなければ、満期償還時に投資額(元本)が戻ってくるほか、定期的に貸付利息を受け取ることが可能です。
なお、債券には公共債や民間債などさまざまな種類があり、種類によって償還期間や利率が異なります。
債券の種類
債券は、発行元によって以下のように呼称や特徴が異なります。
| l 公共債
国や政府系機関、地方公共団体などの公的な団体が発行する債券です。主な種類としては、国債や地方債、政府関係機関債、地方公共債などがあります。 l 民間債 民間企業が資金調達をするために発行する債券です。民間債は、企業が発行する社債(事業債)と金融機関が発行する金融債に大別されます。 l 外国債券 通貨、発行場所、債券の発行者のいずれかが外国の債券です。主な種類としては、円建て外債(サムライ債)、二重通貨建債(デュアル・カレンシー債)、外貨建て外債(ショーグン債)などがあります。 |
債券は、利息のつき方によって以下のように分類されることもあります。
| l 利付債
半年に1回や1年に1回など、定期的に利子が支払われる債券のことです。 l 割引債 利子が支払われない代わりに、発行価格が額面金額よりも低く発行される債券のことです。 |
他にも債券には、新規発行のものか、すでに発行されたものかによって以下のように分類されることもあります。
| l 既発債
既に発行され、流通市場(セカンダリーマーケット)で取引されている債券のことです。すでに流通市場に出回っているので「投資したいタイミングではじめられる」「複数の商品を比較検討できる」といったメリットがあります。 l 新規債 新たに発行市場で発行される債券、まず発行条件が提示され、一定期間、募集が行われるのが一般的です |
個人向け国債とは
債権の中でもよく聞かれる「個人向け国債」について説明します。日本国が発行する債券のうち、個人のみが購入できる債券のこと指します。
国は企業に比べて経済状況や信用状況が悪化するような問題が起こりにくいため、個人向け国債は元本割れのリスクがほとんどありません。個人向け国債の具体的な特徴は、以下の通りです。
| 商品 |
|
| 金利タイプ | 固定金利または変動金利 |
| 金利 | 年率0.05%を下限とする |
| 満期 | 3年・5年・10年 |
| 利払いの時期 | 半年ごとに年2回 |
| 購入金額 | 最低1万円から。購入金額の上限はなし |
| 中途換金 | 発行後1年経過すればいつでも可能 |
なお、国債は金融機関や郵便局、農協などで購入でき、購入手数料はかかりません。ただし、国債を管理する金融機関の口座開設や口座を維持するための手数料は必要となる場合があります。
債券投資の5つのメリット・特徴
一般的に債券投資は、投資信託や株式投資などの金融商品と比べて安全性が高いとされてます。そのため、投資初心者であっても、資産運用しやすい商品の一つです。結論からいうと、債券投資は「大きなリスクをとることなく中長期で資産運用をしたい人」「リスク分散のために投資先を分散させたい人」「仕事のリタイヤをみすえて資産を安定的に運用したい人・資産保全をしたい人」にはおすすめの商品です。
ここでは、債券投資の5つのメリット・特徴について解説します。
相対的なリスクの低さ
債券投資は、償還期限まで債券を保有し続ければ、元本が保障された状態で返還される可能性が高いです。そのため、日々値動きをする株式投資と比べて低いリスクで資産運用を行えます。
債権の中でも、個人向け国債は国が発行している債券であることから、他の発行体の債券と比べても安全性が高いです。また、1万円程度の少額から投資できる点も、リスクを抑えられるポイントになるでしょう。ただし、リスクが抑えられている分、リターンが少ない点には注意が必要です。以下の図は他の投資商品も含めたリスクとリターンの図です。

商品の種類が豊富
前述の通り、債券にはさまざまな種類があります。そのため、発行体や通貨、利回り、償還期間などを吟味しながら、自身のライフプランや投資の目的に合った債券を選ぶことが可能です。
預金より高い利子を得られる
基本的に債券は、銀行普通預金よりも金利が高いです。そのため、銀行に預金するよりも債券を購入した方が高い利子を受け取れます。
日本銀行「時系列統計データ表」によると、2022年3月28日時点における普通預金の平均年利率は0.001%です。それに対して、個人向け国債は最低金利0.05%を定めているため、普通預金と比べて50倍の利率の差があります。
加えて、個人向け国債は債券の中でも利率が小さく、リターンが少ない債券であるため、他の債券であればさらに高い利子を受け取ることも可能でしょう。リスクが低く、預貯金するよりも大きなリターンが期待できるのは債券投資の魅力です。
分散投資に役立つ
債券と株式には、「債券価格が上がると株価が下がる」「債券価格が下がると株価が上がる」といった相関関係があります。そのため、株式投資と債券投資を組み合わせて投資を行うことでリスク分散ができるのです。
この相関関係は、主に以下のような理由で生じるものです。
- 景気がよいと株価が上がり、経済が過熱しすぎないように金融引き締めが起こり(金利の上昇)、相対的に魅力がなくなった債券は価格が下がる
- 株価が下がると株の運用リターンが低下し、相対的に魅力が上がった債券に投資が集まり債券価格が上昇する
関連して「金利と債券はシーソーの関係」とも言われます。金利があがったら債券価格は下がり、金利が下がったら債券価格はあがると言われています。これも相対的な金利と債権の利回り・魅力による変動になります。
換金性が高く、運用途中での売却が可能
債券は株式と同様に、満期まで保有せずに運用途中で市場での売却が可能で換金性が高いです。自分の保有している債券が購入時よりも高く売れれば、売却益を得られます。
ただし、売却のタイミングによっては損失を出してしまうこともあるため、注意が必要です。基本的に、景気が回復し金利が上昇している局面では債券価格が下落し、景気が後退し金利が下がっている局面では債券価格が上昇する傾向があります。
換金性・安全性・収益性などについて債権投資と他投資関連商材の特徴について比較したものが以下になります。安定感がありますが、短期的な収益獲得やインフレ対応には向いていない商品であることもわかります。個々の商品設計目安のひとつとして確認ください。

また投資や投資商品全般についての基本的な考え方について知りたい人は以下の記事を参照ください。
債券投資をする際の5つのリスク
債券投資は安全性が高い投資方法ではあるものの、リスクがないわけではありません。ここでは、債券投資をする場合の5つのリスクについて紹介します。
価格変動リスク
前述の通り、債券は、満期を迎える前に市場で売却し換金することが可能です。しかし、債券価格は日々変動しているため、売却価格が当初の購入価格から下がっている(上がっている)可能性があります。これが「価格変動リスク」です。
債券の価格は、債券の需要と供給や市場金利、信用力の変化によって変動します。満期まで保有すれば価格変動リスクは生じないため、売却すべきかどうかは市場の動向を注視しながら慎重に検討した方がよいでしょう。
信用リスク
信用リスクとは、購入した債券の発行体が破綻したり、財政難に陥ったりすることで事前に決められた利息や償還が受けられなくなるリスクのことを指します。利息の支払いが滞るだけでなく、最悪の場合は元本も返ってこない可能性があります。
信用リスクを避けるためには、発行体の信用度を確認してから債券を購入するようにしましょう。新しく発行する債券の場合は「目論見書」、すでに発行されて市場で流通している債券は「財務諸表」が信用度を確認する手がかりとなります。
また、株式会社日本格付研究所(JCR)や株式会社格付投資情報センター(R&I)、ムーディーズなどの民間会社が発表している格付けを参考にするのもよいでしょう。
格付けとは、発行元の信用度や、利息・元本などを確実に支払えるかの度合いを「A」「BBB」などの記号にて表すことです。信用リスクを測る指標の一つとして使われます。
信用度が高い方からAAA(トリプルエー)からC(シングルシー)までの9段階ありますが、一般的にはBBB以上の格付けを信用度が比較的良好だと考えられる「投資適格格付け」、BB以下を信用度が低いと考えられる「投機的格付け」と言われています。
流動性リスク
流動性リスクとは、債券を希望通りに売れないリスクのことを指します。債券は満期前に市場で売却が可能ですが、買い手が少なければ売ることはできません。たとえ売れたとしても、希望通りの価格で取引が成立せず、売却益を得られない可能性もあります。
債券の流動性は、債券の発行量や需要の高さ、信用リスクの高さなど、さまざまな条件によって変わってきます。あまり一般的でない債券に投資する場合は、流動性リスクに注意した方がよいかもしれません。
カントリーリスク
カントリーリスクとは、債券を発行する国の政治や経済、社会状況の不安定さによって債券価格が変動し、損失を被るリスクのことです。
企業の財務状況などとは無関係に発生するリスクであるため、企業の債券を購入していた場合でも国に何らかの問題が起これば、損失につながる可能性があります。一般的に、中南米やアフリカ、アジアなどの新興国において発生しやすいリスクとされています。
以下は、カントリーリスクが起こり得る原因の一例です。
- 政策変更による民間企業や私有財産の国有化
- 金融システムや税制などの制度変更
- クーデター
- 通貨危機
- 戦争、内戦
為替変動リスク(外国債券の場合)
為替変動リスクとは、為替レートの変動により、利子の受取額や満期時の償還額が変動するリスクのことを指します。
債券には、利子や元本が日本円で支払われる「円建て」と、ドルやユーロなどの外貨で支払われる「外貨建て」の2種類があります。外国債券の場合は、基本的に外貨建てです。
外貨建てで元本などが支払われる場合、円安のときは「円」での受取額が増えるため、利益を得られます。しかし、円高になると「円」での受取額が減るため、損失を被ることになります。外国債券を購入する場合には、利率の高さだけでなく、為替変動のリスクにも目を向けることが重要です。
債権投資の始め方
債券投資を始めるには、債券を扱っている証券会社で口座開設が必要です。証券会社によって取り扱っている債権の種類が違います。なお個人向け国債であれば銀行でも購入可能です。債券の購入方法は「投資信託を購入」もしくは「直接証券会社から購入」の2つの方法があります。
債券といっても多種多様で、特に投資初心者が個別の債権のよしあしを判断するのは難易度が高いです。そのため投資初心者であれば投資信託による債権購入をおすすめします。
国内債券でおすすめの投資信託
投資家から集めた資金を複数の金融商品に投資するのが「投資信託」です。投資信託の中には、債券を中心に運用する商品もあります。ここでは、国内債券を中心に運用されている投資信託の中でおすすめの商品を5つ紹介します。
マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド(年1回決算型)
「マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド(年1回決算型)」は、円建てのハイブリッド債券を投資対象としているファンドです。
ハイブリッド債券とは、株式と債券の両方の特性を持ち、普通社債と比べて投資家に対する債務の返済順位が低い債券のことです。リスクが大きい分、普通社債と比べて利回りが高くなっています。ハイブリッド債の発行主体は、BBB以上の格付けを有する企業ばかりです。円建てのハイブリッド債券を主要投資対象とする追加型ファンドは他にありません。国内債券で大きな運用成果を求める人におすすめです。
| 運用会社 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント |
| 基準価格 | 9,891円(2022/10/3時点) |
| 信託報酬 | 年率0.594~0.77% |
| 純資産 | 2,481.93億円(2022/10/3時点) |
| 主要投資対象 | 日本企業が発行する円建てハイブリッド債券 |
日本物価連動国債ファンド
「日本物価連動国債ファンド」は、物価連動型国債を投資対象としているファンドです。
物価連動国債とは、全国消費者物価指数の動きに応じて元金額や利払い額が増減する国債のことです。物価が上昇すると上昇率に応じて元本は増加し、物価が下落すると下落率に応じて元本が減少します。基本的に、インフレにより物価が上昇した場合でも、元本が目減りすることはありません。通常の債券と同様に、利息分が実質的な利益となります。インフレに備えたいと考えている人におすすめのファンドです。
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
| 基準価格 | 10,161円(2022/10/3時点) |
| 信託報酬 | 年率0.649%以内 |
| 純資産 | 72.98億円(2022/10/3時点) |
| 主要投資対象 | 物価連動国債 |
eMAXIS 国内物価連動国債インデックス
「eMAXIS 国内物価連動国債インデックス」は、物価変動国債を投資対象としているファンドです。物価変動国債は、物価に連動して元本と利息が増減する債券です。債権の価値が目減りすることを防げるため、インフレリスクを抑制しつつ、運用成果を得たい人にはおすすめといえます。
また、他の物価連動国債を投資対象とするファンドと比べて信託報酬が比較的低い点もおすすめできるポイントです。
| 運用会社 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
| 基準価格 | 9,637円(2022/10/3時点) |
| 信託報酬 | 年率0.44%以内 |
| 純資産 | 54.51億円(2022/10/3時点) |
| 連動指標 | NOMURA物価連動国債インデックス |
eMAXIS slim国内債券インデックス
「eMAXIS slim国内債券インデックス」は、日本の国債や社債などの債券市場の動向を表す代表的な指数(NOMURA-BPI総合指数)への連動を目指すインデックスファンドです。
信託報酬が比較的安く、つみたてNISA対象商品の平均的な信託報酬率(年率0.255%)を下回っています。なお、eMAXIS slim国内債券インデックスはつみたてNISAの対象銘柄ではないため、注意が必要です。
| 運用会社 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
| 基準価格 | 9,831円(2022/10/3時点) |
| 信託報酬 | 年率0.132%以内 |
| 純資産 | 169.96億円(2022/10/3時点) |
| 連動指標 | NOMURA-BPI総合 |
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
「三井住友・日本債券インデックス・ファンド」は、日本の国債や社債などの債券市場の動向を表す代表的な指数(NOMURA-BPI総合指数)への連動を目指すインデックスファンドです。
信託報酬がつみたてNISA対象商品の平均的な信託報酬率(年率0.255%)を下回っているため、運用コストを抑えたい人におすすめです。なお、三井住友・日本債券インデックス・ファンドは、つみたてNISA取引銘柄の対象ではありません。
| 運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
| 基準価格 | 12,600円(2022/10/3時点) |
| 信託報酬 | 年率0.176% |
| 純資産 | 740.31億円(2022/10/3時点) |
| 連動指標 | NOMURA-BPI総合 |
※本記事は投資家への情報提供を目的としており、特定商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われますようお願い致します。
債権以外の投資・資産運用方法
これまで債権投資について解説してきましたが、債券投資以外の投資・資産運用の方法についても紹介します。それぞれの方法にメリットや注意点があります。いくつかの選択肢を理解した上で、納得した資産運用をすることが重要です。
投資信託の購入
投資信託は、投資家から集めたお金で、投資のプロが国内外の株式・債券・不動産や金などの現物の商品やその組み合わせによってプロが運用してその利益を分配する仕組みです。
特徴としては
- 運用に手間がかからない
- 少額でも投資可能
- 複数の商品や銘柄によって構成されるため分散投資効果が得られる
といった点があります。投資信託についてもっと知りたい人は以下の記事を参照ください。
ロボアドバイザーを活用した投資
人工知能を活用した投資のサービスとしてロボアドバイザーがあります。ロボアドバイザーは「投資一任型」と「アドバイス型」の2種類があります。
特に「投資一任型」は個人のリスク許容度にあわせて自動で投資をしたり資産のリバランスをしてくれるサービスが多く、投資にあたって時間や勉強・情報収集の手間をかけたくない人にとっては一考の価値があります。詳細は以下の記事を確認ください。
専門家に相談したい人はIFAに相談も
専門家に相談して資産運用をしたい方は、IFAという独立系のファイナンシャルアドバイザーを活用するのもひとつの方法です。証券会社や銀行では販売手数料が高い商品や販売ノルマ達成に資する商品が重点的に販売され、問題になるケースも過去散見されました(もちろん一概にすべての証券会社や銀行がそうであるというわけではありません)。
IFAも色々な事業者がいますが、より中立的で顧客本位な立場でのアドバイスを求めることができると言われています。
IFAについてもっと知りたい方は以下の記事を参照ください。
小口からできる不動産投資 J-REIT(Jリート)
REITとは、オフィスビルや商業施設、マンションなど、さまざまな不動産を投資対象とし、賃貸収入や売買益を投資家に分配する金融商品のことです。不動産を証券化することによって少額から投資ができることになります。株式や投資信託などと同様に値動きは大きいものもありますが、定期的に分配金が出たりインフレに強いなどの特徴があります。大きな元本をかけたり不動産ローンを組んだりすることなく不動産投資を進めたい人にとっては検討に値する選択肢でしょう。
詳細は以下の記事を確認ください。
まとめ
債券投資は、他の金融商品と比べてリスクの低い投資方法です。特に個人向け国債は少額で始められるため、できる限り安全に資産運用を始めたい人に適した商品といえるでしょう。
一方で、安全性が高い投資方法とはいえ、価格変動リスクや信用リスクなどのリスクはあります。元本保証された預貯金と異なり、損失が出る可能性もあることは理解するようにしましょう。
債券投資を検討する特に投資初心者の人は、個別での債権投入よりも債券投資を中心とした投資信託を活用することをおすすめします。
![]()
![]()
難しいお金の話を、ファイナンシャルプランナー技能士や保険・金融商品の専門家が忖度なし「ホンネ」でわかりやすく伝えます。

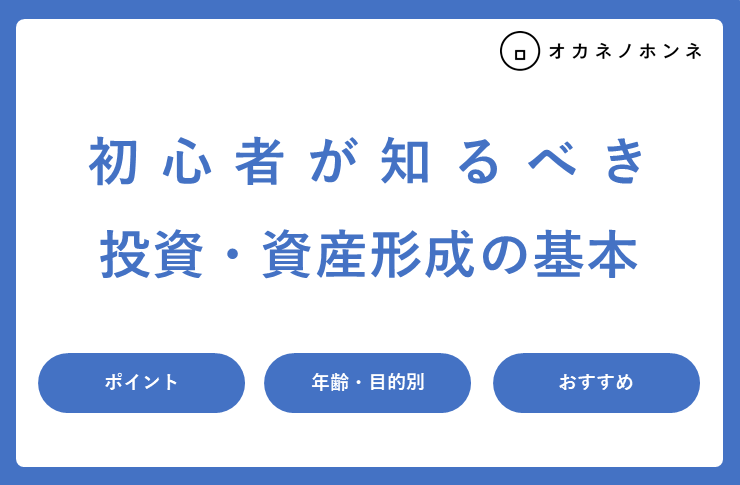
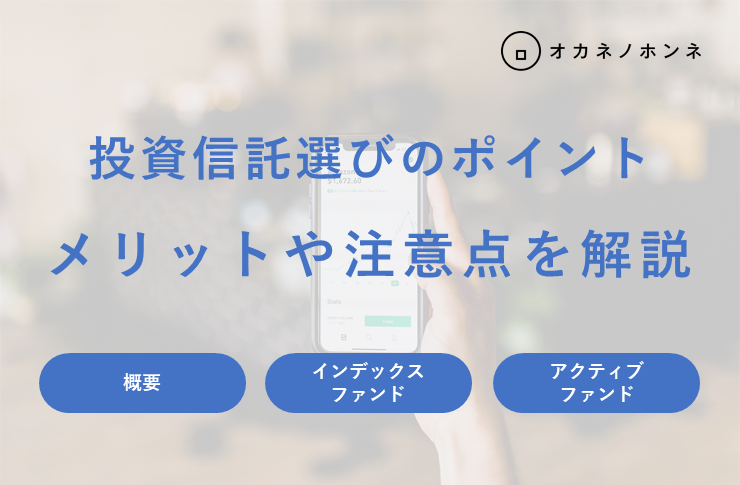

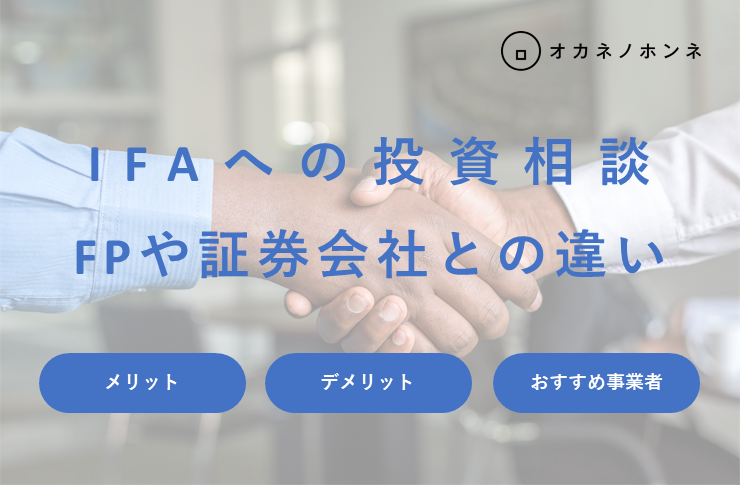
.png)